はじめに
子どもへのお小遣い、どうしていますか?
我が家では、子どもが小学生になるタイミングで、お小遣いをどうすればいいのか考えるようになり、インターネットで情報を集めまくりました。
でも探せば探すほど、いろいろな記述があり、もっとどうすればいいのかわからなくなりました。
お小遣いの渡し方は 大きく以下の3パターンがあります。
・定額制
・報酬制
・必要時払い
どれがいいのかわからなかあったので、色々試行錯誤を重ねた結果、三人の息子たちに合わせた
「我が家流お小遣いのカタチ」ができあがりました。
今回は、わが家のお小遣い事情を具体的に紹介しながら、メリットやデメリット、そして試行錯誤の中で気づいたことをまとめました。お子さんのお小遣いの渡し方に迷ったとき、少しでもヒントになれば嬉しいです。
長男(中3):お手伝い報酬制で「働く喜び」と「家事スキル&交渉力」を育てる

我が家の長男(中3)は、お小遣いに“報酬制”を取り入れています。
最初に、長男の状況を少しだけ説明します。
長男は起立性調節障害があり、現在は自宅での学習を選択しています。学校へは、別室登校や行事への参加、プリント類の受け取りなど、必要に応じて登校する程度です。高校進学は通信制「N高」を予定しており、将来はゲーム制作に関わる仕事を希望しています。そのため、3DCGやプログラミングの勉強も同時進行で続けています。
機材は、マックブックプロやセカンドモニターはこちらで用意しましたが、液タブや書籍、周辺機器は基本的に長男が“自分のお小遣い”で購入しています。必要なものが見つかると、以前よりも積極的に家事に取り組み、報酬を増やそうと努力する姿が見られます。
小学生の頃は定額制を取り入れていて、学習に必要なものは親が購入し、それ以外はお小遣いやお年玉で本人が買う形でした。高価なものは誕生日やクリスマスにプレゼントしていましたが、中学生になり「欲しいものを自分で手に入れる経験を積ませたい」という思いもあって、今の報酬制に落ち着きました。
報酬制の仕組み
家事に応じて金額を設定し、取り組んだ内容を長男が毎日「家事帳」に記入します。必要なタイミングでまとめてお小遣いを引き出せる仕組みです。
金額の一例はこんな感じです
・掃除機がけ……200円
・洗い物……200円(鍋洗いやお米研ぎがあるときは加算)
・弟のお風呂介助……300〜500円(機嫌の悪さレベルで変動!)
体調の波があるため、その日にできる家事を自分で選び、無理のない範囲で取り組めるようにしています。自主性がある分、“イヤイヤ家事”はほとんどなく、ひとつひとつ丁寧にこなしています。
報酬制にしてよかったこと
報酬制を導入してから、見えてきたメリットがいくつもあります。
そして何より、長男は現在不登校という状況で、自己肯定感が下がりやすい時期でもあります。
そんな中で「自分は家族の役に立っている」と実感できることは、彼にとってとても大きいようです。
デメリットもあるけれど…
もちろん、親として少し大変だなと感じる点もあります。
それでも、得られるもののほうが圧倒的に大きい、と感じています。
“交渉力”までも育つ副産物
時々、長男からこんな交渉が入ります。
「今日は〇〇だったから、100円アップになりませんか?」
「〇〇の作業をしたら、いくらになりますか?」
もちろん交渉はOKにしています。
なぜなら、同じ家事でも日によって作業量が違ったり、難易度が変わったりすることは日常的にあるからです。
そして、こうした“交渉の経験”は、将来どんな仕事に就いても役に立つスキルです。
自分の働きをどう伝え、どう評価してもらうか。
中学生のうちから練習できるのは、むしろ貴重な機会だと考えています。
次男(中1):お小遣いは「定額制」でバランスの取れた自主性を育てる

次男のお小遣いは、本人の希望もあり「定額制」を採用しています。
毎月月末に決まった金額を渡し、その月に特別頑張ったことがあれば、追加の特別報酬をつけることもあります。ベースはあくまで定額。その上で“ご褒美加算”がある、というスタイルです。
家事については、平日は通常登校の日が多いため(起立性調節障害が出ると遅刻・欠席の日もありますが)、基本は
・お風呂洗い
・夕食の配膳の手伝い
・布団敷き
を担当しています。
休日は少しボリュームが増えて、
・布団の上げ下げ
・家中の掃除機がけ
・三食の配膳
をこなしています。
次男の良いところは、こちらから声をかけなくても、自分のタイミングで自然とお手伝いをしてくれるところ。
定額制でも“やらされている感”がなく、日々の家事にごく自然に参加しています。
お小遣いを定額制にしたメリット
定額制は、いずれ必要になる金銭管理や“自分で決める力”の良い予行演習になっています。
デメリットもないわけではなく…
このあたりは、定額制の「安心」と引き換えに生まれる“ほどよい甘え”のようなものだと感じています。
次男のお小遣いの使い道
次男はあまり物欲がないタイプで、使う場面といえば
・オンラインゲームの課金
・コンビニスイーツ
がほとんどです。
そして、コンビニに行くと、自分の分だけでなく家族全員の“好きそうなもの”を選んで買ってきてくれます。(これがまた可愛いのですが)でも、お金が一気に減ってしまう原因でもあります。
特にゲームの課金についてはルールを設けています。
「月に1回」「お小遣いの半額まで」
という約束を本人はきちんと守っています。
課金はよくない? それでも許容している理由
正直に言えば、課金は“形として残らない使い道”なので、親としては推奨したいとは言えません。
ただ、
・本人にとって幸福度の高い使い道であること
・娯楽へのお金の使い方を今のうちから学んでほしいこと
・自制心を持って使えるようになる経験が必要なこと
これらの理由から、我が家では「ルールを守るなら課金もOK」にしています。
“報酬”ではなく“お小遣い”だからこそ、次男もお金の使い方について素直に耳を傾けてくれる部分があります。
親子で一緒に考えながら、今の生活の幸福度と未来の生活を両立できるスキルを育てていってほしいと思っています。
三男(小4・最重度の知的障害あり):必要な時に必要な支援をする
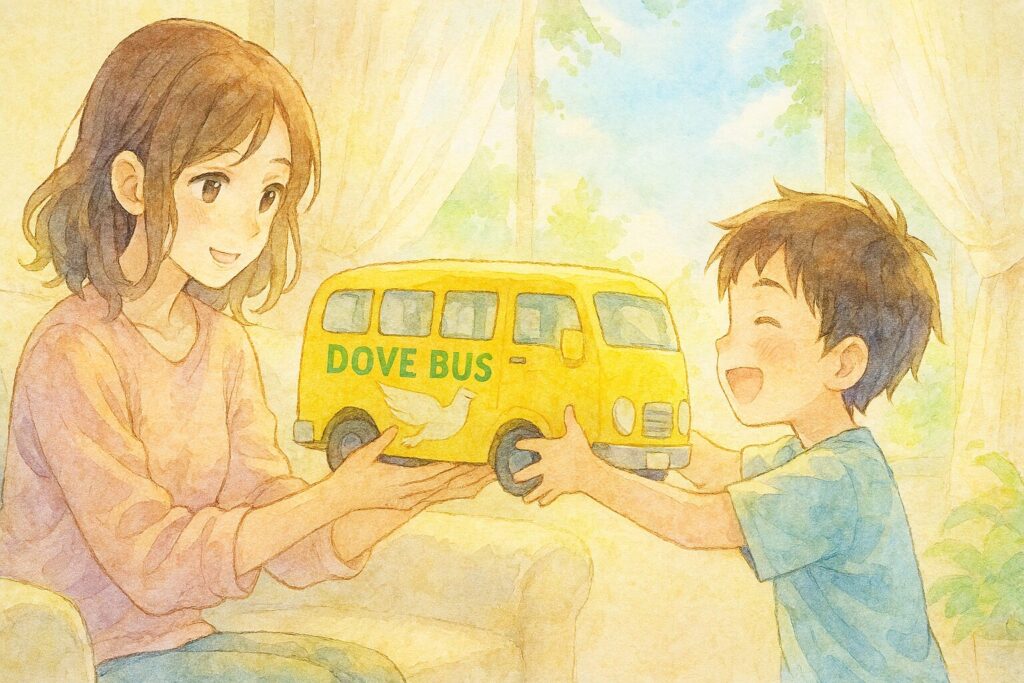
三男(小4・最重度の知的障害あり)には、「お小遣い」という形は設けていません。
言葉がまだ十分に出ず、「〇〇がほしい」と自分から要求することもほとんどなく、まだまだ数やお金の概念が曖昧なため、一般的なお小遣いのルールがそもそも成り立ちにくいのです。
そのため我が家では、三男が興味を持ったタイミングを逃さず、必要なものを“必要な時に”準備する形をとっています。
「今、この子の心が動いているな」という瞬間が何より大切なので、そこを最大限に活かしてあげられるようにしています。とはいえ、実際にそれが訪れるのは年に数回あるかどうか、という程度ですが…。
できれば誕生日やクリスマスなどの特別な日に合わせられるように調整しますが、そうもいかない場合は無理をせず、その時点で“コスパよく”購入できる方法を探します。
三男は物へのこだわりが強い一方で、飽きるのも早かったり、扱いが少し荒くなることもあります。なので、新品にこだわらず、中古品を選ぶこともよくあります。
メルカリやAmazonの中古商品をうまく利用することで、次に訪れる“ほしいタイミング”のために予算を残しておくこともできます。
メリット
デメリット
ただし三男の場合は、最重度の知的障害があり、さまざまな発達がゆっくりです。
そのため、お金の管理や買い物の仕方を学ぶことは、今はまだ優先順位が低く、「生活の中で安心できる体験」「好きなものと出会ったときの喜び」を丁寧に積み重ねていくほうが大切だと考えています。
いずれ成長と経験が重なり、タイミングが来たときに、少しずつ「お金との関わり方」を一緒に練習できたらいいなと思っています。
お小遣い制度を通して見えてきたこと
兄弟がいると、どうしても「平等にしなきゃ」と思ってしまうものです。
けれど、お小遣いに関しては“数字の平等”よりも、実は「子どもたち自身の納得感」が何より大切なのだと感じました。
同じ兄弟でも、性格も、生活リズムも、興味関心も、発達のスピードもまったく違います。
家庭の事情だって当然それぞれ。
だからこそ、
「世間ではこの年齢なら◯◯が普通らしい」
「◯歳からはこうあるべき」
といった“よその基準”をそのまま当てはめても、自分の子どもとピタッと合うことなんてまずありません。
大切なのは、
その家庭、その子に合ったルールをつくること。
そして、子どもの成長や状況に合わせて、そのルールを柔軟に変えていくこと。
社会の目安や一般論はあくまで“参考書”であって、その家庭の“答え”ではありません。
わが家の場合も、三人三様の方法をとっていますが、それぞれの方法がベストだと思っているわけではなく、
「今のその子にとって一番しっくりくる形」
をその都度選んでいるだけです。
お小遣いは単なるお金のやり取りではなく、子どもが自立に向けて小さく一歩を踏み出すチャンスでもあります。
完璧じゃなくていい。
家庭ごとに違っていい。
親子で話し合いながら、少しずつアップデートしていけば、それがその家族にとっての最適解になるはずです。
まとめ:お小遣いは「家庭教育」の入口

我が家では、三人の息子たちに対して、それぞれの性格や発達状況、生活スタイルに合わせて
「報酬制」「定額制」「必要時払い」
という三つの方法を使い分けています。
どの方法にもメリットとデメリットがあり、完璧な答えはありません。
大切なのは、
今のお子さんにどんな力をつけたいのか、
そしてお子さん自身が何を求めているのか、
親子で話し合いながら決めていくことだと感じます。
お金の管理は、社会で生きていくうえで欠かせない力の一つです。
大人であっても無駄遣いをしてしまったり、家族の状況が変わるたびに収支の調整をする場面があります。
そう考えると、お小遣いは“人生の小さな練習ステージ”のようなもの。
だからこそ、家庭内でお金のことを一緒に考え、時には見直していくことには大きな意味があります。
それぞれの家庭にそれぞれの事情があるように、お小遣いの形も家庭の数だけ存在していい。
今回のお話が、みなさんがお子さんのお小遣いについて考えるときの、ちょっとしたヒントになれば嬉しく思います。

コメント